こんにちは!ママ薬剤師M子です。今回は、虫刺されの市販薬についてお伝えします。
休日や夜間に限って、「かゆいー!」って大騒ぎ。そんな時、本当に頼りになるのがドラッグストアの市販薬だと思います。
でも、いざお店に行くと、色々なOTCの薬がずらーっと並んでいて、「え、どれがいいの?」「うちの子にはどれが合うの?」って迷っちゃうこと、ありませんんか。
そして今回注目したのが、気が付けばいつも実家の棚の上にあった『キンカン』。そしてその近くの棚の引き出しに入っていた『ムヒ』。もしかすると、この記事を読んでいただいている方のご家庭にも、常備されていたかもしれません。

前回までは、病院のお薬を解説しましたが、今回からお近くのドラッグストアで手に入る虫刺されのお薬、特に昔ながらのお薬について解説していきますね!
今回は、虫さされ対策に焦点を当てながら、従来の『キンカン』と『ムヒ』のドラッグストアでの選び方を解説していきます。と同時に、この2つの商品がなぜロングセラーとして長年愛用されているのかも探ってみたいと思います。
「キンカン」も「ムヒ」も、現在実に多くの商品が販売されていて、ステロイドやかゆみ止めの成分が違うもの、剤形もムヒにおいては液体からクリームタイプまで様々です。今回は、すべての商品の比較ではなく、コアとなっているロングセラーの商品に絞って解説することで、他のキンカンとムヒの商品や、キンカンとムヒ以外のOTCを選ぶ際のポイントも考えやすくなるといいなと思っています。
虫刺されの市販薬:なんで効くの?キンカン・ムヒの成分をチェック!

パパママは世代によると思いますが、少なくともM子にはおなじみの「キンカン」と「ムヒ」。どうして虫刺されのかゆみや炎症に効果があるのか、その秘密を探ってみましょう!
M子としては、外で走り回っていた子供時代を思い出すパッケージですが、れっきとした『第2類医薬品』としてドラッグストアまたは薬局で販売されています。
キンカンについて解説します!
キンカンといえば、あの独特のツーンとしたアンモニアの香りと、塗った時のスーッとする感じが特徴ですよね。
以下の、主な有効成分が5種類配合されています。それぞれの特徴や注意点について見てみると以下の通りです。
- アンモニア水(参考2)
- 効果:アンモニア水単独でも虫さされによるかゆみへの効果が報告されている
- 特徴:ツンとした刺激性のにおい、常温(15-25℃)では揮発性が強い
- l-メントール(参考3)
- 効果:虫さされには、清涼感を与え、その刺激により痒みをしずめる効果が期待できます。
- 特徴:爽快な芳香(ハッカの匂いをイメージ)や、矯臭(ぎょうしゅう、臭いを抑えたり隠したりする作用)作用がある
- d-カンフル(参考4)
- 効果:局所刺激作用、血行の改善、炎症を鎮める、痒みを鎮める効果があり、筋肉痛、打ち身、皮膚の痒み、凍瘡などに用いられる。虫さされには、痛みをとったり、痒みを和らげたりる効果が期待できます。
- 特徴:天然の樟脳(しょうのう)のことで、医薬品として指定されていて、芳香(防虫剤、楠の木のイメージ)がある。
- サリチル酸(参考5)
- 効果:炎症を抑えたり、角質を柔らかくしたりする働きがあるほか、弱い抗菌・防腐作用もあり、角化症や湿疹、アトピー性皮膚炎、乾癬、白癬(水虫)やその他の角化性の皮膚の疾患などに用いられる。
- 特徴:虫さされによる痛みや不快感、赤みや腫れを抑える効果、虫さされによる肌の硬化を改善する効果、感染を防ぐ効果などが期待できます。
- トウガラシチンキ(参考6)
- 効果:虫さされのところの痛みや痒みを和らげてくれる効果が期待できます。
- 特徴:皮膚刺激剤として、筋肉痛、凍瘡、凍傷(第1度)、育毛などに用いられる。
キンカンは、それぞれにしっかりとした効果をもつ成分が複合的に働くことで、虫さされのさまざまな症状を和らげてくれるようですね。

キンカンという名前から、果物の金柑の成分が入っていて肌に優しそう~なんて連想していたこともありましたが、金柑の成分は皆無でした・・・
キンカン利用時の注意点
キンカンはアンモニア水、トウガラシチンキなど文字だけでもわかるくらいの刺激の強さ、アンモニア水の揮発性などの問題があり、注意点が明記されているのでまとめました。
- 使用年齢について
- 年齢は制限の記載がないですが、添付文書には「乳幼児は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください」との記載があるため乳幼児には自己判断での使用はNGです。
- 保存方法について
- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓し立てて保管→持ち運びや車内放置はNG
キンカンは褐色(茶色)瓶に入っていますね。この理由は、単に昔から褐色瓶だったからというわけではなく、キンカンにはアンモニア水などの揮発しやすい成分が入っていて、光によって揮発しやすくなってしまうため、光が直接当たりにくい褐色の瓶が使用されているのだそうです。
- 火気のある場所
- エタノールが溶剤として含まれているため、引火を防ぐため、使用する際には火気から離れたところで使用する必要があります。
- 目に入った場合
- アンモニアなどの成分による内容だと思いますが、眼に入ると結膜や角膜に炎症を起こすことがあるため、眼に入らないように注意する必要があります。
- 使い方について
- 塗って乾かす、塗って乾かすを繰り返す必要があります。
- 主な副作用
- 副作用には皮膚の発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、ただれ、灼熱感などがあり、使用後にこれらの症状が現れた場合、または5~6日間使用しても症状がよくならない場合には使用を中止し医師、薬剤師または登録販売者に相談する必要があります。
ムヒS
続いて、ムヒについてみていきたいと思います。ムヒには「液体ムヒS」や「ムヒアルファEX」など、いろいろな種類がありますが、キンカン同様、昔ながらの「ムヒS」について詳しく成分を見ていきましょう。
- ジフェンヒドラミン塩酸塩
- 効果:かゆみの原因となるヒスタミンの働きをブロックする「抗ヒスタミン成分」により痒みを鎮めル効果が期待できます。
- グリチルレチン酸
- 効果:生薬カンゾウ由来の成分で、炎症を鎮める効果が期待できます。
- l-メントール
- 効果:キンカンにも入っている成分で、清涼感を与え、その刺激により痒みをしずめる効果が期待できます。
- dl-カンフル
- 効果:清涼感を与えて、痛みや痒みを和らげる
キンカンにも入っている成分と同じ?と思いきや、カンフルの前のアルファベットが若干ちがいます。(d-カンフルがキンカンで、dl-カンフルがムヒSです。)これは、自然由来(d-カンフル)か化学合成由来(dl-カンフル)かの違いになります。それぞれで一部用途が異なる部分もある医薬品添加物ですが、今回の虫さされへの目的としてはほぼ同じだと思われます。
- イソプロピルメチルフェノール
- 効果:殺菌作用により、掻き壊してしまった部分からの細菌感染に効果が期待できます。
『ムヒS(参考7)』は、かゆみを抑える成分や炎症を抑える成分、そして清涼感を与える成分などがバランスよく配合されているのが特徴です。
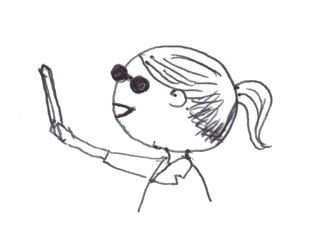
どちらにもℓ-メントールが入っていて、塗った瞬間すーっとしますよね。ただ、キンカンの場合は、アンモニアが入っているためツンとした感じの好みがわかれるところだと思います。
この記事のまとめ:キンカンとムヒS、どう違うの?
今回は、昔から日本の家庭で愛されてきた虫刺され薬の代表格、『キンカン』と『ムヒS』の成分と特徴を詳しく見てきました!最後にポイントを振り返ってみましょう。

こうして比べてみると、同じ虫刺され薬でも全然アプローチが違うのが面白いですよね!「どちらが良い・悪い」ではなく、それぞれの特徴を知ることで、ご家庭に合ったお薬を選びやすくなりますね。M子の家に両方あったのも納得です。
次回予告:結局どっち?キンカン・ムヒを選ぶポイントを徹底解説!
さて、今回はロングセラーの「キンカン」と「ムヒS」のポイントを解説しましたが、いざドラッグストアに行くと、キンカンとムヒはどう使い分けたらいいの?について書いていきたいと思います。
年齢や症状、使い方に合わせた「キンカン・ムヒを選ぶポイント」を解説します!
ぜひ、次回の記事もチェックしてくださいね!
誰かの役に立ちますように。
最後までお読みいただきありがとうございました。
ママ薬剤師M子
【参考文献等】- 厚労省HP[↩]
- アンモニア水添付文書[↩]
- l-メントール添付文書[↩]
- dl-カンフル添付文書※d-カンフルは今はほとんど作られておらず、dl-カンフルの添付文書のみです。人工のものか合成のものかの違いで効果効能は同じです。[↩]
- サリチル酸添付文書[↩]
- トウガラシチンキ添付文書[↩]
- ムヒS添付文書[↩]
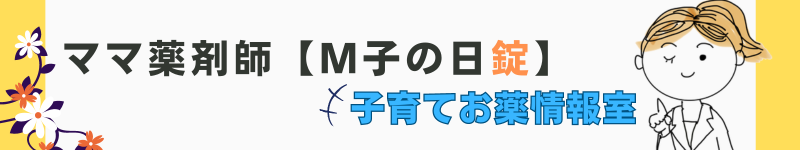
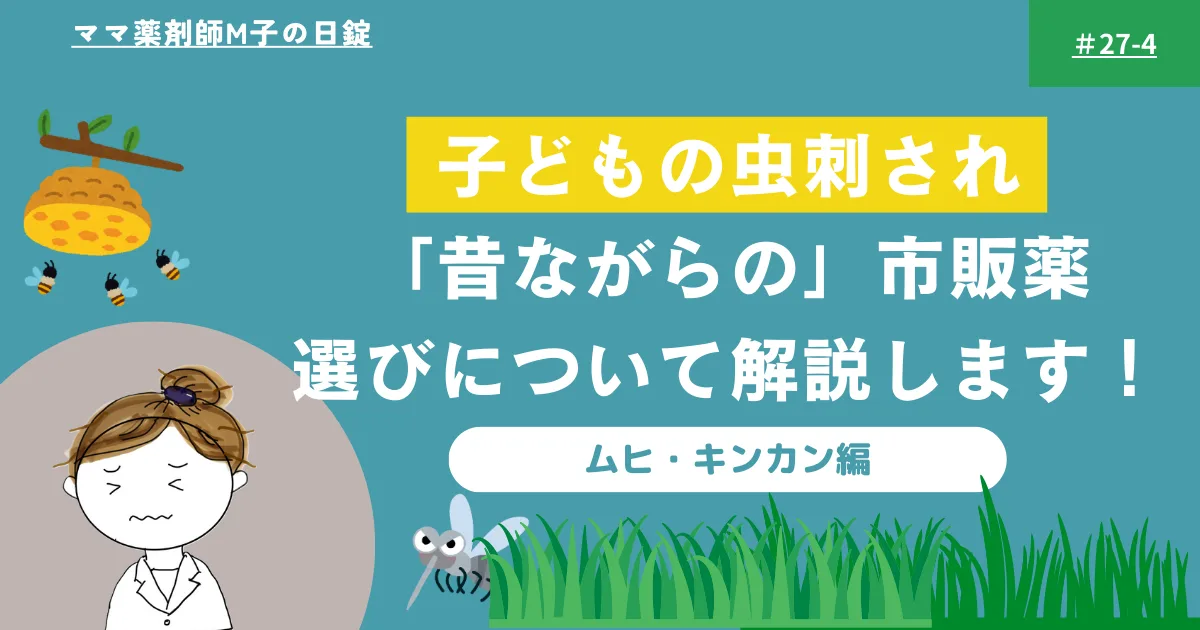
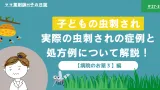
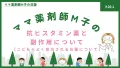

コメント